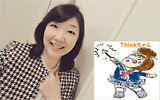"SF inside" Day 2019
自分から始めるSF
2019年6月22日(土) - 23日(日)
@
ちよだプラットフォームスクエア(東京都千代田区)
“SF inside” Day 2019 当日の様子
“SF inside” Day 2019 参加者インタビュー
"SF inside" Day 2019 大会テーマについて
「何が問題なのかを知っている」という側に立つことは簡単で、「~だからダメなんだよ」というセリフが頻発され、重いトーンの会話が続くことがよくあります。スケープゴートが見つかれば、その存在を責めることで自分は正しいという側に居続けることはノーリスクで快感すら覚えます。しかし、問題を解決する主体になろうとすれば、勇気や覚悟を必要とします。そして始めたことがとても小さくて、いまだ解決につながるように見えないレベルの時でも、恥ずかしさや自己卑下したくなる感情をやり過ごして、前に進み続けるにはさらに勇気と自己信頼を喚起する必要があります。
「自分から始めるSF」というフレーズは、そんな勇気を発揮した人たちにそのストーリーを語ってもらい、それがこれから何かを始めようとする人たちの背中をそっと押すことになれば"SF inside" Dayにふさわしいという想いで大会テーマとしました。
僕にとっては、14年前に株式会社ソリューションフォーカスを設立して、その当時はメンタルヘルス領域以外ではあまり知られていなかった「解決志向」の考え方を、ビジネス領域で応用してもらえるような普及活動を始めたことが「自分から始めるSF」にあたります。
▼ クリックして続きを読む ▼
思い返してみると、「コンプリメント」という専門用語を「OKメッセージ」と再定義してみたり、「人は肯定された時に変化の余裕を持つ」という金言フレーズを前面に掲げてみたり、国内外のSF実践家の様々な創意工夫を自分なりにアレンジし直したり、そういった人々が集い学び合うための大会を創設したり、その他大小色々なことをよく「始めた」ものだと思います。それらのことの中にはまったく芽が出なかったり、出てもすぐにしぼんでしまったりしたものも沢山あります。逆に、予想外に人気を博して継続するプログラムに発展したものもあります。「うまくいけばもっとやる。うまくいかなければ違うことをやる。」というSF原則に則りつつ、自分から始めたりやめたりしたことに、悔いが残ることはありませんでした。
セラピストでない自分がセラピー領域で開発されたものを違う分野で応用するということで、教科書が存在していない分だけ、自分流の解釈を自己責任で押し通すという側面がありました。そして、それに共鳴してくれる人がいて、その結果有用な行動変容が起こるのであれば、それは自分の解釈が有効であるエビデンスだと受け取りました。それは「自分から始める」ということの醍醐味として味わうことができました。また、その体験はさらなる工夫をするための原動力となりました。何を参考にしようが、どんな用語を使用しようが、そこに「自分から始める」「自分なりに工夫してみる」という要素がある分だけ、生きたエネルギーが生まれます。形式的に正しいかどうかよりもその生きたエネルギーを注入することが人を動かすのだと思います。今までSF活用事例共有大会を続けてきて、事例発表をしてくださる方たちのその「自分から始める」エネルギーに接することで、私自身毎回新たな勇気をいただいてきました。本当にありがたいと思います。
"SF inside" Day 2019が皆さんのそんな生きたエネルギーを交換する場となりますように!
一つひとつの事例紹介文は末尾にある「クリックして続きを読む」をクリックすると全文が表示されます。。
<全体会>
言葉の魔法使い「和」
~製品と共に流れるSF~
|
 |
藤森工業株式会社(ZACROS)
名張事業所
東瀨 和明氏
(写真中央) |
(製造課 梱包工程リーダー
SF実践コース10期) |
中内 素貴氏
(写真左) |
(製造課 職長
SF実践コース4期) |
西岡 理氏
(写真右) |
(品質保証課 専任
SF実践コース2期) |
|
|
[SF実践の内容]
〈FP 言葉の魔法使い〉
私が「SF実践コース」に参加しFP(フューチャーパーフェクト)として掲げたのは「言葉の魔法使い」です。「言葉の魔法」は私にも皆さんにも始められるSF(ソリューションフォーカス)だと思います。
〈言葉の魔法とは?〉
皆さんは前向きな気持ちになる歌の歌詞、勇気づけられる映画のセリフ、優しい気持ちになる絵本に出会った経験はありませんか?私は、心を動かす力を持った言葉を「言葉の魔法」とよんでいます。
人は楽しいと声を出して笑い、笑顔の人を見ると自然に心が和みます。「言葉の魔法」は普段の会話の中にもたくさん隠れていて人を和ませるパワーを持っています。
〈言葉の魔法の使い方〉
私が目指す「言葉の魔法使い」とは、人と話す際に「どうやったら解決方向へ気持ちを向けてくれるんやろか」「どんな言葉をかけたらプラス思考になってくれるんやろか」と考えて会話の中にSFを取り入れ、話した相手が気付かぬうちに解決への一歩を踏みだすきっかけを作る人です。
|
▼ クリックして続きを読む ▼
「言葉の魔法使い」になれば家族や友人を笑顔にし、雰囲気の良い職場を作ることができるのではないかと思います。
〈言葉の魔法使いの実践〉
私の所属する名張事業所では、主に医薬品の包装材料を製造しています。様々な行程を通り梱包工程は工場内の最終工程になります。私の業務の一つとして各工程への資材の運搬があり、工程や製品の流れをさかのぼりながら各工程にいる仲間たちと話をするきっかけがあります。
一緒に働く仲間たちの行動や言動を観察し長所や課題を見つけ、彼らの愚痴や悩みを受け止めて「言葉の魔法」をかければ解決方向へ導けるのではないかと考えました。
それぞれの工程で一人一人と丁寧に会話し「言葉の魔法」と一緒に蒔いたSFの種が製品と共に梱包室まで流れ、SFが事業所全体に広がるようにと実践してきました。
「言葉の魔法使い」は仲間たちをよく観察する事を大切にしています。仲間たちの声に耳を傾け、何を考え、何を思い、どうありたいかを会話の中から拾い集め、否定的な言葉は使わずに普段は人から褒められないような、当たり前で小さなリソースに焦点をあてたOKメッセージを送るようにしました。
〈実践の成果:梱包工程の成長〉
梱包工程リーダーとして梱包メンバーとのコミュニケーションを取る際も「言葉の魔法」を使いチーム全体の結束力・モチベーションアップも試みました。
以前の梱包工程はお互いに我関せずの殺伐とした雰囲気が漂っており、まず私はメンバーを知るために面談をしました。
『面談=固いもの』のイメージを取り払いたいと思い「ドラえもんのひみつ道具で欲しいものは?」のような会話が膨らむ質問を考え、梱包メンバーそれぞれの考え方、仕事に対する想いや家族への優しさなど沢山のリソースを引き出すことが出来ました。今後も『メンバーとの距離を縮めるための面談』として年2回の実施を目指していきます。
また、梱包メンバーにプロ意識・自律心が芽生えるような言葉をかけました。
「梱包室は工場内最後の工程です、お客さんに一番近い工程・お客さんが最初に見るのは梱包された製品であることを意識してください」
「ステップアップするために出来る事 どんな小さな事でも見付けてチャレンジしてください」
そして、SF実践コース10期生から得た朝ミーティングのアイデアを取り入れた「朝の小話」をすることでメンバー同士が互いに興味を持つようになりました。
今では事業所で一番結束力の強い工程と言われ、工場内最後の砦として梱包プロ集団と胸を張れるほど成長してくれました。
急な休日出勤にも率先して「私が出勤します!」と言ってくれる人がいたり、犬猿の仲と言われていた2人が今では仕事に対して衝突せずに意見を言い合える仲になり、別のメンバーとも話をしながら帰宅する様子も見る事ができました。そして、毎月の生産性ノルマを1年間達成し続け2018年度を終えることができ、梱包メンバーの自信に繋がる成果を出すことが出来ました。
[ハイライト]
工程リーダーとして仲間に生産性ノルマにとらわれずプロセスに重点を置いた作業を意識してもらいました。自分が出来る小さな一歩を見付けて、「一歩前進、成長できた!」を共有することで1人1人がチームとして必要な人材である事を実感してもらいました。
人により言葉のとらえ方が違うので、日々仲間たちを観察しリソースを探し、その人に合った最適な「言葉の魔法」をかけるようにしました。実際にどのような言葉を使ったのかは、当日の発表の中で具体的に紹介いたします。
また、発表ではいくつかの実践事例と共につい言ってしまうあるあるPF(プロブレムフォーカス)言葉と私がかけた「言葉の魔法」を並べ対比することで、みなさんに身近に感じてもらえるように作成した資料を使います。
[発表者からのメッセージ]
私のテーマ・実践事例は仕事でもプライベートでも共感してもらえる場面があります。色々な立場や環境の人にこの共感を実践として使って欲しいと思っています。
名張事業所から一緒に発表をしてくださる西岡さん、中内さんはSF実践コースの先輩であり、素晴らしいソリューショニストで名張事業所のSF風土を作ってくれています。
西岡さん、中内さんと一緒に和やかで楽しい発表をしてまいります。
そして「言葉の魔法使い」に終わりは無く、これからも事業所全体にSFを広めていきたいと思っています。
<分科会1>
組織や個人の変化を誘発した
「SF的ワークショップの企画実施事例」 |
 |
彼谷 浩一郎氏
| "between the noses" corp. 代表 |
|
|
[SF実践内容およびその成果の要約]
わたしは大手銀行系IT企業でプログラマー、システムエンジニア、プロジェクトマネジャーを20年経験し論理的思考とロジカルシンキングを身につけ、目標を達成し業績をあげてきた。
予期せぬ人事異動で人事部企画担当になり論理的思考で人材育成の企画実施をした。テクニカルスキルのトレーニングは順調に進んだが、ヒューマンスキルのトレーニングで思うような効果を出すことが出来なかった。そこで文献を調べ、各種勉強会や人事部門交流会に参加し、各種研修にも参加し、コーチングのトレーニングそしてコーチング資格の取得にも挑戦した。しかしなかなか答えは見つからない。ある人事部門交流会で「彼谷さんの考え方ってこの本に書いてあることと共通点が多いですね」と書籍「解決志向の実践マネジメント」を勧められた。私とソリューションフォーカスの出会いだ。
リーダーシップやマネジメントのようなヒューマンスキルには「正解はない」。会社や人事部が考える「リーダーシップの発揮の仕方、マネジメントのやり方」(答え)を提供するのではなく、参加者個々人の経験の中から参加者各自のやり方に気づく機会を提供することが重要である。そこで参加者の気づきを誘発するトレーニングを企画実施することを目指した。
|
▼ クリックして続きを読む ▼
所属する企業の中で管理者全員を対象に「ピープルマネジメント研修」「リーダーシップワークショップ」を企画し約300名に実施、現在も継続して実施中である。同時期にIT系企業8社が集まる人事勉強会で「IT業界の次世代リーダを育成したい」との話が持ち上がり8社共同でトレーニングの企画を進めた。「参加者の気づきを誘発するトレーニング」の提案をしたところ各社の共感を得ることができ合同でトレーニングカリキュラムを企画した。2009年からワークショップを実施し約500名が参加しいまも継続的に実施している。
[ハイライト]
★SF的なワークショップの取り組み姿勢:
- 講師ではなくファシリテーター
- 解決の糸口は参加者の会話の中にある
- 褒めるのではなく変化に気づく
- 良いところを伸ばすではなく出来ていないことが少しでも出来た時を見逃さない
- 多様性を重んじる。絶対に否定しない
- 声なき声を拾う
- 机は使わず椅子だけで車座になる
- 参加者同士ができるだけ多くの参加者と話せるように配慮する
- 笑いを大切にする
- 参加者が考え続けるように質問を投げかけ続ける
- エドワード・L. デシの動機づけ理論を実践する「自律性」と「有能感」
★SFツールをうまく使えた、自分独自で工夫をした点:
- 「リフレクティングチーム」の「明確化の質問」に「ソリューションカード」を利用
- 「OSKARモデル」を独自に改定したワークシートを作り、ステップごとにペアワークを実施。その後個人でワークシートに書込む
- OSKARモデル
| OUTCOME |
ゴールを確認する |
| SCALE |
1-10のスケーリング |
| KNOW HOW |
スケールを1ポイントあげるための工夫 |
| AFFIRM |
OKメッセージ |
| & ACTION |
実行 |
| REVIEW |
振り返り |
★SFの効果が示されたと思うこと:
「自分の経験、知識、成功、失敗」「チームのメンバー」「家族」「苦手な上司」全てが
リソースになり得ることを参加者の方々の言葉から感じた
★実践のなかで感動したこと:
参加者の声「今まで受けた研修の中で一番楽しかった」「全く眠くならず2日間がアッという間にすぎた」「全ての社員に受講させたい」「自分にもできると思えるようになった」「今まで会社に行くのが嫌でしたが、明日会社に行くのが楽しみです」
[なぜ事例発表をするのか?]
今まで企画・実施したワークショップ(15年間約750日のべ約15,000名)でのSF活用事例(SF活用は2008年から10年間)をみなさんと共有し、みなさんのSF活用に活かしていただくとともに、今までの自分自身のワークショップを振り返り、みなさんからのフィードバックを受け自身のワークショップの質の向上を図りたい。
[どんな方に参加して欲しいか?]
組織、チーム、個人の変化を誘発したいと思う方すべてに参加してほしいです。ワークショップの企画実施事例ですが、ポイント活用も可能なので講師や人事企画以外の方もぜひ参加してください。
例えば
- チームミーティング、会議、を楽くしたい方
- 社内、社外の勉強会を企画する方あるいは企画したいと思う方
- 自分自身の変化を誘発したい方…自分の可能性に気づき新しいことが始めたくなるかも???
- もちろん講師、ファシリテーターの方またはこれから講師、ファシリテーターをされる方
自律した現場づくり
~ハッスルソリューションを通して自発的に!~
|
 |
藤森工業株式会社(ZACROS)
横浜事業所
工藤 翔太氏
(写真左) |
(製造1課SF実践コース10期) |
桑本 丈弘氏
(写真右) |
(製造課班長SF実践コース9期) |
|
|
[SF実践内容及びその成果の要約]
【背景】
私は製造機械のオペレーターで、主に日用品の詰め替え用の袋を製造していますが、私から見た現場が仕事に対して自発的な動きが少ないと感じたので、もっと前向きな(自発的)現場に変えたいと感じていました。
【SFとの出会いによる変化と抱いた想い】
- 仕事に対して迷走、落ち込んでいるときにSF実践コースに参加していた前任者からオスカーモデル形式で質問してもらいました。その時落ち込んでいる気持ちが和らぎ、前向きに考えられるようになったことからSFに対して興味が沸き、SFを学んでみたいという想いからSFベーシックおよびSFフォーラムに参加する決意をしました。そして、それらのセミナーを通して感じた感動を現場の皆と共有したいと思うようになりました。
- その後、SF実践コースに参加。自分にできるSF実践をして現場に貢献しようと思いました。
【実践してきたと】
- OKメッセージ作戦:
まず私がすぐにできるSF実践として取り組んだのが「OKメッセージ」です。毎日1回良かったな、ありがたいなと素直に思ったことに対してOKメッセージを現場の皆に伝えました。その中でOKメッセージの効果を実感したことがありました。後輩指導の中で教えたことがすぐに出来たことに対して、「出来てるじゃん!自信を持って出来ていることは良いね!」と言ったところ、「はいっ!」と普段は自信なさげな後輩から自信たっぷりな返事が帰ってきたことに驚き、OKメッセージを出した私も嬉しくなりました。
|
▼ クリックして続きを読む ▼
- 皆に「バディーシステム」についてインタビュー:
前任者が取り組んでいた「バディーシステム(5に説明あり)」を現場の皆がどう思っていたか、一人ひとりインタビュー形式で聴き取りをしました。一人ひとり生の声が聞きたかったので敢えて紙にせず直接聞きました。結果は良い、悪いさまざまな意見をいただきました。少し皆の本音が聞けて嬉しい気持ちになりました。
- 今一度バディーシステムを皆に説明:
インタビューを踏まえ今一度バディーシステムの目的、取り組むことでどんなメリットがあったのか説明しました。ここで現場の皆からたくさん意見が出ると思ったのですが皆まじめに聞いてくれはしてもあまり意見が出ず、自分の想像と違い少し寂しいなと思いました。
- 皆に現場をどう変えたいか自分の想いを伝えた:
次に自分のこれまでのことと現場の皆が仕事に対して前向きになってほしいという自分の想いを伝えました。その時の皆の反応は少しの驚きと、下を向いていた顔が上がって頷きながら話を聞いてくれたので、嬉しい気持ちになりました。
- 「バディーシステム」の形を少し変え「改善会議」の実施:
「バディーシステム」とは目標管理の手法で、作業員が2人1組でバディーを組み目標の進捗内容をメンター(班長)→マネージャー(職長)と報告します。報告内容に対しアドバイスをマネージャー(職長)→メンター(班長)→バディー(作業者)へと返すことで目標が共有でき、成長力を加速するための相互支援ができるシステムとしてもともと意図されていました。
それを3人1組のトライアングルバディーに少し形を変えました。そして「目標管理」で取り組んでいたバディーシステムから、「改善会議」としてトライアングルバディーで取り組むことにしました。2人より3人1組にする事でより多くの意見が出て改善スピードも速くなるのではと思ったからです。改善会議では目的を見える化し、何の為にやっているかを意識してもらうように工夫しました。また「会議」という硬いイメージを払拭する為、参加しやすいミーティング名を皆で考え、「ハッスルソリューション」と名称を変えて進めています。「ハッスルソリューション」の名前の由来は当日の発表でのお楽しみです。最初は皆「また新しいことが始まった」と疑心暗鬼でしたが、今では1人ひとり発表内容が皆に伝わるよう写真を入れるなどの工夫をして前向きに参加してくれています。
[ハイライト]
- 実践で一番最初に取り組んだOKメッセージ作戦。最初はなかなか恥ずかしく言い出せなかったのですが、SFクリードにもある「認め合う」を意識し相手を見ることで自然とOKメッセージを出すことができました。OKメッセージを伝える際気を付けたことは相手の良い部分を見ずに褒めてしまわないようにしたことです。相手のこと(内容)を見て良かったな、ありがたいなと素直に思ったことに対して良かった、ありがたかった内容を添えてOKメッセージを伝えるように心がけました。
- バディーシステムを少し形を変え臨んだ「ハッスルソリューションン」。現場の皆が参加しやすい、改善しやすい、発言しやすい会議体にするためにアンケートを取り、コミュニケーションをとり、工夫をして取り組みました。会議体の目的を表示し現場の皆に意識して取り組んでもらえるよう工夫しました。ハッスルソリューションの中で意識したことは“小さな○を大きくする、伸ばす”ことでした。一つ一つの工夫が功を奏し、最初は疑心暗鬼だった現場の皆も、「なぜやるか」の目的を理解できたことで、全員が自主的に改善策に対して向き合い、前向きに会議に参加してくれるようになりました。
[発表の場および今後に期待すること]
分科会では皆さんから「トライアングルバディー」「ハッスルソリューション(改善会議)」に対する アドバイスをいただくなどの意見交換ができたらと思います。
フューチャーパーフェクトのその先、ハッスルソリューションを継続させ現場の皆が前向きに、働きやすい現場に変化させられるよう、自分にできるSFを続け貢献していきたいと思います。
答えはその人の中に 希望は私達の中に
──SZC(サイゼリヤカフェ)まなぴーVer.── |
 |
株式会社サイゼリヤ
螺澤 富江氏 (写真左から2人目)
(t-FACE店・リーダー) |
|
|
[SF実践内容およびその成果の要約]
- 「まなぴー」とは:
仕事のモヤモヤを話し解決に向け何ができるかを考え、意見を出し合い学び合う場です。
- 「まなぴー」を始めたきっかけ:
私は組合役員として多くの組合員と出会い、交流を深めてきました。その中で私達と同じ立場(定時社員)の方々は、話を聴いて欲しい、大変さを分かって欲しいという思いが強いと感じていました。私達には横のつながりを作る機会はほとんどありません。自分にももやもやする思いがあり、仕事に対する思いや考えを話し合える機会を作りたいと思っていたからです。
- 「まなぴー」の約束:
「コンプる(SF)」のスイッチを入れて過ごす。
お互いを尊重する。
- 概要:
開催頻度:月一回(3月と8月は除く)
時間:11:00~15:00
場所:サイゼリヤ店舗
- SFに関する主な取り組み:
「OKメッセージを送り合う」「いいとこ探し」をベースにして様々なワークを行っています。例:「自分が朝起きてからここに来るまでにあった良い事を3つ書く」「自分が仕事で頑張っている事を話す」etc. 詳細は当日のお楽しみに。既開催回数は現時点で11回です。
|
▼ クリックして続きを読む ▼
- うまくいった事:
SFのスイッチが入るようになった事と、メンバーにとって安心・安全な場になっている事です。難しかった事は日程を合わせる事でした。今は最後に次回の日にちを決める為、定期的に開催できるようになりました。
また、SFについて楽しく取り組めるよう工夫が必要だったのですが、回を重ね気づいたメンバーの変化は、大きく分けて2つあります。
1つはみんなが話す気満々で参加するようになった事です。どんな事を聴いてもらいたいかを、ある程度決めているようで、「えー、何にしよう?」「有りすぎて決められない。」という言葉が減り、スムーズにワークに入れます。2つ目は何かあると自分が悪いと思いがちだったのが、落ち着いて振り返る。意見をもらう。自分で考え次に繋げることができるようになってきた事です。また最近社内プロジェクトにおいても、クルー中心の同様の活動がSZC(サイゼリヤカフェ)として注目されつつあります。
[ハイライト]
「まなぴー」は変化しています。始めはSFに慣れる事を意識したワークを中心に行ってきました。最近は仕事でたまったもやもやを吐き出した後、解決に向けた小さな一歩を決めて取り組む事を中心にしています。OSKARの型やリフレクティングを使いますが、その中で苦労したのが質問の仕方でした。考えすぎて黙ってしまう場面が何回もありました。そこで自分達の質問を振り返ったり、質問の仕方や例を学びました。その中で焦点を本人に当てると良いことが分かりました。繰り返すうち、少しずつ良くなってきています。
「まなぴー」を始めてから一番感動したのは、話し手が何をしたら良いか分からない状況から、質問に答えるうちに自分ができそうな事を見つけられた体験です。「あ、それにしよう。これならできそう!」とその人が言った時、ぱっと表情が明るくなったことが忘れられません。後で「本当は仕事を辞めようと思っていました。でももう少しやってみようかな。」と打ち明けてくれました。辛さが希望にかわったと思いました。なかなか状況は変わりませんが、それでもこの場が私達にとって元気を取り戻す希望になっています。
。
[今後への期待]
今期待するのは、それぞれが自分の店で「まなぴー」をやる事です。できないことをどうしたらできるだろうか?とみんなで考え、お互いを尊重し学び合えることが増える事を密かに願っています。
[意見交換したいトピック]
「ありがとう」が伝わりにくい人と仲良くする方法。「できない」理由を探してしまう人が一歩踏み出そう!と思える背中の押し方。
<分科会2>
学校・職場のSF-Wi-Fiをオン!にする
― ひとりの心理士が自分から始めてみたSF風土づくり物語 - |
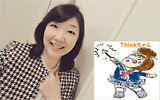 |
中村 亜紀子氏
|
|
[物語の要約]
九州・大分を中心に活動するフリーランスの心理士が、週に複数の学校や職場をかけもち、いじめや友人関係の問題、上司‐部下の関係について、ものの考え方について、ハラスメントについて、病気・復職についてなどを、相談室でカウンセリングを行いながら、そのサポートをしていました。
SFA(Solution Focused approach)、その他のスキルやアプローチ法を使いながらカウンセリングをする中で、笑顔で帰って行く生徒や働く人たちを、相談室から見送りながら、あることをきっかけに、「この繰り返しでいいのかな…??」と、疑問を持つようになりました。元々カウンセリングには、個人に関わるカウンセリングと、集団に関わるグループカウンセリングというものがあります。教室、部活動、所属、職場、、、と、相談者が帰って行く「グループ」にアプローチする必要があると強く思った時期でもありました。
そんな中、SFAを集団に活かす考え方を、福岡でのSF基礎コース(「SFベーシック」の旧バージョン)で学び、相談者が戻っていく学校や職場のSF風土づくりを目指して、また相談者自身のSF力をアップさせることを目指して、カウンセリング業務と同時進行で、自分なりのSF活動を始めたのでした。
|
▼ クリックして続きを読む ▼
少しずつ生徒に向け、先生に向け、働く人に向けて、SFをキーワードとして取り入れた講演会の定期開催、継続的な研修会の実施が増えていきました。言いたいことはその回数ではなく、参加者が、研修後にSFを使ってもらうことが何より大切と考え、それについての工夫を凝らしたことです。
「ひとりでSFを広げることは難しい」と思い込んでいた私ですが、自分なりのSF活動を、各学校や職場で伝えて続けていくことで、「やっぱりあのSFっていいですね!」、「うちのクラスで、職場で、活用するにはどうしたら良いでしょうか?」と言ってくれる人が増え、結果として、SFのWi-Fiエリアが増えていくように、広がっていくのでした。
衝撃だったのは、「プラスのめがねのお話を聞いた学年と、そうでない学年では全然違うんです。またあのお話をしに来てくれませんか?」と、突然かかってきたある先生からの電話でした。その日から私のSF-Wi-Fiのレベルは増していき、機運が高まっていくのです・・・。
この発表は、私、心理士自身をSFの基地局として、SFのWi-Fiエリアを広げるように、「SFっていいね!→こんな風に、SFを使ってみたよ!」と言ってもらうために、そしてSFインサイドの集団(グループ)を増やしていくために、カウンセリング、研修会、講演会、そして雑談までも!工夫を凝らした10年越の物語です。
[物語のハイライトは2つ!]
- ハイライト①
「プラスのめがねのお話を聞いた学年とそうでない学年では全然違うんです!」
──もしもあなたが、どこかの会社や学校で、SFについての話をしてだいぶ経ってから、こんな風に言われたら、どんなことを想像しますか?どんな変化を期待しますか? その答えは、生徒のアンケートに散りばめられていました。「ひとりでSFを広げるなんて無理」とあきらめモードだった私自身のSF‐Wi-Fiはこの瞬間、最強レベルで、オンになりました。生徒のアンケートの言葉やA学校での活動とともにお伝えします!
- ハイライト②
B企業内相談室で、心理カウンセリング業務を担うことになったある春。SFインサイドの職場を作るという夢が叶う時が来た♪と思ったのも束の間・・・簡単ではありませんでした。しかし学校でのSF‐Wi-Fiの例で考えれば、当然のことでした。焦りは禁物と、頭を切り替えて、自分なりの小さなSF活動開始です。そんな中、メンタルヘルス予防を目的とした管理職向けの研修会を実施することになりました。しかしどうやって、SFを職場に導入するのか??
試行錯誤しながら、担当者と「SFを始める」ことをチャレンジし、協議しながら、ついに「いいね!の木」を茂らせた現在進行形のお話です。担当者の生インタビューも予定しています。
[うまくいったと思えた工夫TOP3]
- 相談者が相談室から教室、職場に戻っていったあと、ひとりでもSFを考えることができるツール『こころのアシアト日記』を作成しました。
- SFに奮闘する『Think(シンク)ちゃん』♪ 相談室で出会った生徒の描いたキャラクターです。
- 問題が浮上したり、業務量がいっぱいっぱいの時に、Facebookのいいね!みたいに、軽く共感したことを伝える、こころが動いたことを伝えるための『いいね!の木』を考案しました。
[苦労をしたけれど、それを乗り越えることができた体験]
こころの態度(attitude)を決めて臨んだことです。何よりも、だれよりも?!SFの可能性を信じている私自身が、自分に対してSFで考えないことは、大きな矛盾があると考えました。心の底からそう思えた時、乗り越えるというより、これほどパワフルで、わくわくすることはありませんでした。
[発表者からのメッセージ]
SFの良さは知ってるけど、実際に使えていないという声を、耳にします。SF‐Wi-Fiは、知識を入れることよりも、使うことでオンになります。どう使うかに、決まりもルールもなく、アートなSFだからこそ、発信者が、創意工夫し、楽しんで使うことが、周囲に伝わって、いいね♪使えるね♪と思って頂けるのだと思います。ご自身の職場、地域、家族に、SF‐Wi-Fiを広げていきたいとお考えの方、この物語に興味を持ってくださった方、お待ちしています!健康経営や学校・学級運営に興味をお持ちの方も、是非!
施設間バリアフリー
~事業所の枠を越えた人材交流、組織の見えない障害を取除く~ |
 |
藤森工業株式会社(ZACROS)
沼田事業所
|
|
[SF実践内容およびその成果の要約]
〈背景〉
弊社には全国7か所に生産拠点がありますが、うち2拠点は群馬県に置かれています。現在、私はその中のひとつである沼田事業所に在籍し、生産機のメンテナンスや営繕を担う部署(技術課 施設)に従事しています。
最近、一部組織の再編により、特殊な技術・知識を必要とする業務が各生産拠点に移管されることになりました。業務は移管されても技術や知識の習得には多くの時間を必要とし、簡単に引継げるものではありません。おそらく他事業所でも同じ悩みを持っているのではないか?そう考えた私が導き出した結論が、事業所という枠を越えた連携を目的とした「コラボレーション」です。先ずは群馬県内のもうひとつの拠点であり、製造している製品と生産機が似ている昭和事業所とのコラボを「SF実践コース」に参加するにあたっての取組テーマとし、2018年9月から実践を始めました。
〈取組〉
- 準備と共有
- 沼田事業所 施設メンバーの特長探し:
先ずは自分のSF力の向上を図るために、プラスの眼鏡を使ってみました。活動の中で欠くことのできない施設メンバーの特長を捉える事ができました。かつて漠然としていたものが明確になり、 敬意を持って接する事ができるようになりました。
- トラブル対応でのSF活用
|
▼ クリックして続きを読む ▼
-
- 最初のSFの活用でした。突発的な生産機の故障ではありましたが、SMSを利用してトラブルに対応しました。各自が自主的に策を講じ、共有しながら解決させることができました。
- 沼田事業所 施設メンバーとオスカーモデル:
毎月実施している施設会議の時間を割いてもらい、方向性の確認と意思統一を図るべくオスカーモデルによるミーティングを実施しました。テーマは「理想の施設像」です。私自身も施設係員のひとりとして参画し、回答しながら方向付けを行い、コラボレーションという「目的」を共有することができました。
- 活動開始
- 昭和事業所へのアプローチ
コラボへ向けて最初の一歩でありましたが、拒否されたらコラボは終了に成りかねない緊張する場面でした。沼田で実施したオスカーモデルの結果を利用してアポイントを取り、打合せを打診しました。その結果、昭和事業所から施設担当者2名が来所して打合せを開催する事になりました。
- 昭和事業所 施設2名とオスカーモデル
沼田と同様にオスカーモデルを使って昭和の「理想像」を引出しつつ、目的の共有を図ろうと画策しました。しかし、それが安易だったのか? 昭和にSFの要素がないからなのか?拒絶されてしまい諦める事になりました。ところが、ここから始めた井戸端会議が功を奏し、昭和事業所の想いを引き出すことができました。後に諦めたのはオスカーモデルによるアプローチだけで、「傾聴」「OKメッセージ」「うまく行かない事はやめて、別の事をやる」など実はそこにも多くのSFの要素があった事に気付きました。
- 混迷と気付き
偶然でありましたが昭和事業所とのコラボレーション案件が舞い込みました。展開には恵まれましたが、自己満足するための活動になっているのではないか。私が抱くSFのイメージと現実とのギャップに
このまま進めて良いものだろうか?迷いが生じました。しかし、そんな迷いから解放してくれたのは
やっぱりSFでした。実践コースのセミナーの中で「応援し合う」仲間が気付かせてくれたのは「SFの
環境」でした。
- コラボレーション
- 昭和事業所の設備把握
やりたかった事に気付き、迷いから解放されて開き直ることができました。そして環境作りを意識しながらの取組みになりました。先ずは昭和事業所をしっかり理解するために、設備改造工事の手伝いを目的に昭和事業所を訪問しました。改造工事を進めるなかで、ベテラン担当者による人材育成や心遣いに感動をさせられました。心を開いて接することで、多くの事を話していただき、学ぶ事が できたと思いました。
- 改善の相互展開
沼田事業所の改善事例をアピールし昭和事業所が展開を検討するまでに至りました。改善した設備の視察に、昭和事業所から2名の施設担当者が来所しました。ここでは、目的の共有と協力関係を作る事に注力しながら設備の案内を実施しました。その甲斐あって、施設業務の経験が浅い担当者の不安を払拭し、展開を確約する事ができました。規模こそ小さいですが「SFの環境」も伴った、思い描いたような「自分らしい」コラボレーションが構築できたと思っています。
- まとめ
私は学生時代にサッカー部に所属していました。試合中にボールを持った時、敵も味方も自分を中心に動きます。プレッシャーはありますが、とても楽しい瞬間です。そこから次に繋げるプレーがうまくいった時は気持ちがよく、とても嬉しいです。監督ではなく、キャプテンでなくても「フィールドでは中心」 になれる。これまでSFを実践しているなかで、それと似た感覚がありました。
また「環境」が最も大事だと感じました。SFを実践する中では、あまりにも当り前すぎて気付くのが遅くなりましたが、背中を押すことができる感覚も得たと思っています。今後も活動を継続していくにあたり「認め合う」環境作りに注力したいと思います。
[ハイライト]
- SFを実践する中で、SFツール(考え方やコミュニケーションモデル等)をうまく使えた、あるいは自分独自にうまい工夫をしたと思える点
グループのなかでオスカーモデルを使い、自らも参画して一緒に回答しました。これによりグループを向かいたい方向へと導き、思いをより深堀する事ができました。
- 大変な苦労をしたけれど、それを乗り越えることができた体験
昭和事業所との打合せでは、型にはめようとして拒絶されてしました。しかし、その後の井戸端会議では昭和の思いを引出す事ができました。この時は「傾聴」する事、「OKメッセージ」を伝える事を継続できたこと、また「うまく行かない事はやめて、違うことをやる」が実行できました。現在は昭和事業所の担当者もコラボレーションに理解を示してくれ、協力して頂いております。
- もっともSFの効果が示されたと思うこと(エピソード)
実践を進める中で、私が抱いていたSFのイメージと活動から得られる手応えにギャップを感じ迷ってしまいました。そんな中で迎えた実践コースの中間セミナーでは、違和感の原因を知りたくて、「否定的なご意見も聞きたいです」と前置きしてから現状を報告しました。そんな中でも沢山のOKメッセージをいただき、また前向きになれました。この集いでは決して変わる事のない「応援し合う」関係、そして背中を押してもらう感覚…気付いたのはSFでは当たり前の「環境」でした。これ以降は迷うことなく自信を持って活動を続けることができました。
SFの効果をもっとも感じたのは、自分自身だったと思います。
- 自分が感動したこと
改善の相互展開では、昭和への設備導入と協力を約束しました。しかし、対応して頂いた2人はまだ施設での経験が浅く、不安である事が見て取れました。そこで私はこんな質問をしてみました。「もし2人がこの設備を導入するとします。その時一番の協力者は誰ですか?」すると2人から「林さんですね。」との答えが帰ってきました。再度、目的を共有している事をアピールしたところ、こんな事をいってくれました。「それでは遠慮なく連絡させてもらうし、手伝いもお願いする。だから我々が必要な時は声を掛けてほしい。」
私にとって何にも代えがたい嬉しい言葉でした。規模こそ小さいけれど、認め合う関係も伴った「自分らしい」コラボレーションができたと思えた瞬間でした。
- 大会テーマ「自分から始めるSF」に関連づけられる点
気が付いた時、思い出した時、何時でも手軽に始められる事が出来るのがSFの良いところだと思います。分科会の場では、おまけとして紹介したいと思いますが、SFの取組により周りの反応が変わっていく様子に気付いた時は感無量です。
また、周囲のSF的言動や行動に気付ける自分でいる事も大切にしています。時々自然とSFを活用している人を見かけますが、そんな方達に意識をしてもらう事ができれば、また違った手応えを感じてもらえると思います。
[発表の場、および今後に期待すること]
今回、私の取組みの発想は課題を共有し効率よく処理するために、事業所という枠を超えて協力することでした。とりあえずコラボレーションのイメージは共有できたと思っています。まだこの活動は始まったばかりで課題は山積みですが、継続して取組み、結果も出せたら嬉しいです。
今回、実践をした感想として、SFでは定石である「認め合う」「高め合う」この環境が大切だったと感じました。こんな環境をどうすれば築いていけるのか?どうすれば継続できるのか?参加して頂ける皆さんとディスカッションさせていただきヒントを掴めたらいいなと思います。
楽しい毎日
~みんなが笑顔で気持ち良く仕事ができる環境にする~ |
 |
藤森工業株式会社(ZACROS)
静岡事業所
大川 利光氏 (写真左から3人目)
(総務課長SF実践コース10期) |
|
|
[SF実践内容およびその成果の要約]
入社後、製造課一筋32年の私が2018年4月中旬より総務課を兼務することになりました。
総務の内容は全く解りませんでしたが、受け持っているルーチン作業内容が多く、出張や有休等で
数日間不在にするとそれらの仕事が滞ってしまうので、出張や有給で不在になることが困難でした。
毎朝行っている課内ミーティングでは、挨拶に覇気がなく、話をしている時でも下を向いていて、
問いかけに対しても反応が弱く、笑顔も少ない状態でした。
それに比べて製造課では集団作業が多く、挨拶も覇気があり、自分なりの考え・意見・提案が
積極的に出てきていたので、違和感を覚えてしまいました。私の取柄は“明るく元気よく”なので、
この性格を活かし、総務課を笑顔で楽しく仕事ができる環境に作り変えたい!と思いました。
|
▼ クリックして続きを読む ▼
私のその想いをSF実践コースにて「実現した後の具体的様子」の絵で表現(総務課内の様子)して
みました。私の想いが実現した後の様子は『みんなが笑顔で助け合い楽しんで仕事をしている姿』:
- 助け合いながら仕事をして色々な業務を覚え、多能工化できれば有給が自由に取れる。
- 自由に有給が取れれば、プライベートで楽しむ事(旅行など)ができる。
- 楽しんだ事を職場で話せば、みんなも同じような体験や行動を取るようになる。
- 今度はどの様に楽しもうか考え、仕事にも張り合いが出て、楽しく仕事ができる。
- そうなると人生が楽しくなり、バラ色の人生となる。
という事を思い描きました。
恥ずかしながら、私が描いた絵(楽しい毎日)を総務課員の皆さんに見せ「皆さんが気持ちよく仕事が
できる環境(雰囲気)を創りたい」と私の想いを伝えると、課員の皆さんは笑いながら聞いてくれました。
同時に出来る事からスモールステップを始めました。
- <褒める:出来ていること・出来たこと・やってみたことなどにOKメッセージを出してあげる>
「流石」「よく思いついたね」「やってみて」「凄いですね」「なぜ分かったの?」「なるほど」など、あらゆる場面でOKメッセージを伝えています。言われた本人は『当たり前』の事かもしれないですが、私にとっては感謝の気持ちや行動してくれたことに嬉しく言葉を掛けています。
※何事にもプラスのメガネを掛け見るようにしています。
- <元気よく挨拶:すがすがしい気分になる事と来所された方に好印象を与える>
「おはよう」「お疲れ様」「ありがとう」「助かります」と元気よく接していることで、他部署の内気な人が気軽に声を掛けてくれたり、相談事や冗談も言ってくれるようになりました。
- <SFの仲間をつくる:仲間をつくることで、事業所全体が気持ちよく仕事ができる環境に変わる>
所長に「静岡事業所を変えて行くために部下をSFベーシックコースに行かせたい」と気持ちを打ち明け相談し、2名が「SFベーシック」を受講させてもらいました(総務課員ではなく技術課員と製造課員)。
そのSFベーシックを受講した2人は、受講後に話し方に変化があり、以前のようなトゲがなくなり、
ワンダウンポジションで相手と接し、物事をプラスのメガネで見るようになり、以前より楽しいと感じる 場面も多くなったと話してくれました。
では、私はどの様に変わったのか振り返ってみました。まず一日楽しく仕事ができるように朝ミーティングでは、前日の面白かったこと・楽しかった事・良かった事などを、みんなに報告する場を設けました。
すると、「今日は寝ぼけてパジャマで来ちゃいました。」とか「休みにおいしいラーメン屋に行ってきた。」など楽しい話が出て、みんな笑顔が絶えなく楽しい一時を送っています。ミーティングの進行役はそれまで私が行っていましたが、その場の“長”の気分を味わってもらうよう今は順番制でみんな楽しみながら行っています。
次に行なったことは、助け合い、活き活きと仕事ができ、有給も気兼ねなく取れる職場に変えるために
「働きやすい職場」のアンケートを取ることでした。アンケートの内容は、みなさんが「働きやすいと感じる職場はどんな職場なのか」、今の状態をスケーリングしてもらい、「働きやすい職場にするために自分で出来ること」を書いてもらいました。有休取得についても現在の状態をスケーリングして、有給を取りやすくするために自分で出来ることを答えて貰いました。
アンケート結果で、みんなが思い描く「働きやすい職場」とは、働く環境が大切であることが分かりました。また、有給取得のアンケートで「取りやすくするために自分が出来ること」という問いかけに対しては、助け合う事が必要でコミュニケーションが大切だという事が分かりました。このアンケート結果を課員と共有し、みんなで「働きやすい職場」に変わるよう提案活動を利用して、誰でも対応ができる仕組みづくりを行なっています。
自分の描いたフューチャーパーフェクトに向け、上手く行かなかった事や失敗もありますが、何事も前向きに行動を取り、実現させたいと考えています。
[ハイライト]
- SFを実践する中で、SFツール(考え方やコミュニケーションモデル等)をうまく使えたり、独自に
うまい工夫をしたと思える点:
- 私のフューチャーパーフェクトを描いたことで、方向性がぶれずに進められています。
- フューチャーパーフェクトに近づけるためのスモールステップを生み出し実践することができました。
- スケーリングをすることで、今どの時点なのか分かるようになりました。
- 小さな変化に気がつくプラスのメガネで物事をみて、次の行動に移せました。
- 苦労や失敗を乗り越えた体験:
スモールステップとして課員との呑みにケーションの場では、毒の吐きだしや自分の取り柄を聞き出すことを目的としたのですが、課員よりOKメッセージを戴き、自分が酔い潰れてしまい上手く聞き出すことができませんでした。しかし、「自分の長所を3つ教えて」とアンケートで聞き出せているので、個々持っている良いところを上手く引き出し、活用していくのが、今後の宿題です。
- もっともSFの効果が示されたと思うこと(エピソード):
実践コースにて肯定質問やアドバイスを頂き、次に繋がるスモールステップのひらめきがあり、何事も 前向きに進められました。例えば、一日を楽しく過ごせるよう朝の課内ミーティングで面白かった・楽しかった事を話すようにしたことやアンケートでみんなに聞いてみる事等です。思い描く事=頭の中で描き・行動を取る。これは、まさしく「アート」だと思います。
- 自分が感動したこと:
実践している中で、小さな変化への気づきがあります。今まで自発的に話さなかった方が、積極的に発言したり、相談に来るようになっています。以前は「課長、これどうしますか?」って聞いてきたのが、今では「大川さん、これやっておきました!」と笑顔で話すようになり、この活動は間違っていない、継続して行きたいと感じた瞬間です。
- 大会テーマ「自分から始めるSF」に関連づけられる点:
- 難しく考える必要はなく、プラスのメガネで見てみると色々小さな変化があり、毎日が楽しくなります。
- 何気ない一言で自分も相手も変われる事。
- 思い描いたアートは実践して、新たなアートが生まれる。
[発表の場および今後への期待]
- まだ出来ていない・新たに出てきたスモールステップを進めて行く:
- 課員に自分たちのフューチャーパーフェクトを描かしてみる。
→課内ミーティングか個人面談で進めてみる。
- 同じような体験をした方がいましたら、成功した事例やアドバイスを戴きたいです。
→何かヒントになる事を学び、実践してみる。
- 課員に明確な目標(仕事・プライベートでも何でもOK)を持たせて、SFで学んだスケーリングやSFカードを使いながら、小さな変化に気づき毎日を楽しんで貰いたい。
- 静岡事業所を、来場された方や他事業所の人たちに「静岡事業所にもう一度来たい」と思わせる環境にしたく、事業所にSFの仲間を増やして行きます。
PAGE TOP